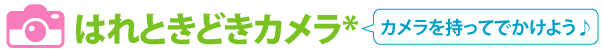前回の記事では「比較と競争、そして反応とか」と題して、趣味がたのしめないと感じる事例についての考察をお届けしました。

今回はその続きです。
趣味は娯楽
趣味は「自分がたのしむためのもの」であり「自分が満足するためのもの」です。
当然のことながら、「そこに他者の関わりが必須」ということはありません。
自分だけでたのしむのが向いている人もいれば、他者と関わりながらたのしむのが向いている人もいます。
そう、趣味というのは、こうした点も人それぞれなのですね。
自分の時間に「他人の存在」は必要なのか
ところが今は、「他者と関わりながらたのしむのが主流(あるいは当然)」といった空気が目立つ時代になっています。
そのため、本来は「自分だけでたのしむのが向いている人」までもがそこに入り込み、あれこれと苦しんでいる――そんな風潮になってきているように感じることがあります。
昨今の強く漂う「目立ったもの勝ち→多くの人がそれに引っ張られる」という空気が影響している部分もあるかと思いますが、それだけではないように感じます。
これまでの記事でも書いたような現象――つまり、「趣味のたのしみ方すらもマニュアル化してきている」という点が大きいのではないかと思います。
たとえば、
- この趣味を始めたら、SNSにアップしなければいけない
- その趣味を持つ人たちとつながりを持たなければいけない
- たくさんの反応を得られるようにならなければ価値がない(と考えるようになる)
などなど、少し極端な書き方ではありますが、妙な形ができているように感じることがあります。
それらが本当にたのしくて仕方がないと感じるのであれば問題はないのですが、「やらなければいけない義務になっている」ように感じる場合は注意が必要です。
「自分がたのしむ時間に、他人の存在って本当に必要なのかな?」――こうしたことを自分の頭で考えるのは非常に大切なことかと思います。
まとめ
今回の連載では趣味についてあれこれと書いてきました。
大切なのは
- 趣味は自分が満足するためのものであり、自分の心を豊かにするもの
- 趣味は自分の時間をたのしむものであり、どれだけ歩みがゆっくりでもよい
- 趣味は苦行ではない
といった点です。
趣味は基本的に娯楽なんですね。
たのしみ方は人それぞれなのですから、「ほかの人がこうしているから、自分もそうしなくてはいけない」ということはありません。
特に今の時代は、「趣味であり、自分のたのしみのはずなのに、ほかの人のことを気にしすぎて苦しくなっている」状況が目に入ることがよくあります。
自分の時間に彩りを与えてくれるもの。それが趣味であり、比較や競争・他人の反応で、そのたのしさを失うのはもったいないと思います。
そもそも「たのしい」と感じるのは自分なのですから、自分が基準でいいのですね。