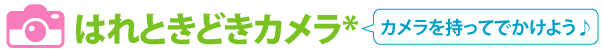前回の記事では、~【情報の取捨選択】「保留する」という選択肢~と題して、情報の取捨選択をする際の注意点についてお届けしました。

今回はその続きです。
「今判断するのは保留」という選択肢
前回の記事では、情報を取捨選択する際のおすすめの方法として、「取り入れる・取り入れない」のほかに「今判断するのは保留」という選択肢をつくるアイデアをお届けしました。
情報の取捨選択の選択肢を2つではなく、
- 取り入れる
- 取り入れない
- 今判断するのは保留
といった形で、3つにする方法ですね。
今回は、その3つめの選択肢「今判断するのは保留」についてくわしくみていきます。
あとでみられるようにしておく
「今判断するのは保留」に振り分けた情報は、今すぐ必要なものではありません。
ですので、今すぐ自分の中に取り入れたり、記憶しておいたりする必要はありません。
「今判断するのは保留」にあてはまる情報は、要は
- 今はわからないけれど、いずれ判断できる時期がくる(だろう)情報
のことです。
ですので、どんな形でもいいので、あとからみられるようにしておく必要があるのですね。
その方法は自分がやりやすい形で構いません。
メモをしておく、スクラップをとっておく、ブックマークをしておく……など、自分がわかりやすければ、どんな形でもOKです。
判断はいつしたらいい?
「今判断するのは保留」にあてはまる情報は、今の時点では「自分にとって必要か不要か」の判断がつかない情報のことです。
言い方を変えれば、いずれ判断できる時期がくるかもしれない――そんな情報です。
が、この「いずれ判断できる時期」というのが、「いつなのか」はわかりません。
「一晩寝て冷静になってみたら」かもしれませんし、「ある程度、自分のスキルが上がってから」かもしれません。
ですので、「今判断するのは保留」に分類した情報を整理できる時期は「情報によってバラバラ」と考えます。
また、必ずしも、最終的にすべての情報を「取り入れる・捨てる」に分類する必要はありません。
先ほども書いたように、判断ができる時期がきたときに「取り入れる・捨てる」を決めればいいので、「長い間、保留に入ったまま」という情報があっても問題ありません。
情報の取捨選択をするメリット
取捨選択をする癖をつけていくと、自分の中で「情報を選択する基準」が確立していきます。
今回の例でしたら、「自分に必要な情報どうか」が判断基準になるわけですね。
こうした考え方に慣れてくると、「あきらかに不要な情報」は瞬時にカットできるようになっていきます。そのため、余計な情報に振り回されにくくなります。
また、「何の身にならない情報を追ってしまい、無駄な時間を過ごす」ことを減らすことも期待できます。よかったら参考にしてみてください。