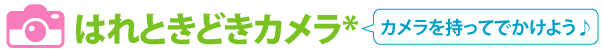前回の記事では「仕上げの手軽さ」と題して、カメラのオートモードについての考察をお届けしました。

今回はその続きです。
自分で「味付けをする」ということ
デジタル一眼で撮った写真データは、基本的に「見栄えがよくなるようなチューニング」はされていません。いうなれば、余計な味付けがされていないバニラ状態なんですね。
それは、自分で味付け(仕上げ)をしなければ、なんとも味気のない写真になりやすいということでもあります。
このあたりは、普通に撮ってもある程度「見栄えがよくなるようなチューニング」をしてくれるスマホのカメラとの大きな違いでもあります。
オートモード
デジタル一眼のその傾向はもちろんオートモード(オートで撮る)でも同様です。
デジタル一眼の画像処理エンジン自体がそうした方向性で設計されていますので、「見栄えをよくしよう」と思ったら、やはり自分でなんらかの味付けをする必要があります。
この仕様は、手軽に見栄えのいい写真をつくりたいときには不向きで、「なんのための(あるいは誰のための)オートモードなのか」と考えると、中途半端なもののように思えてならない部分があります。
結局は、「それなりに味付けをしなければ、いい形にはなりにくい」わけですからね。
この連載でも何度か触れてきましたが、「オートであれば、味付けも(ある程度までは)してほしい」――デジタル一眼を初めて手にした人の中には、そう望んでいた人も実は多かったのではと思います。
手間をかけずとも、それなりに撮れる――これが実現できていれば、今とはまた状況が違っていたようにも思います。
俯瞰できるかどうか
つづいて「俯瞰のしやすさ」という点についても考えてみましょう。
同じ写真でも、「パソコンのモニターでみる」のと「スマホの画面でみる」のとではずいぶんと印象が変わります。画面の大きさが違うので、受ける印象も変わるわけですね。
画像の補正や加工に焦点をあてるのであれば、画面が大きいほうが快適に作業がしやすい印象があります。
が、「写真として仕上げる」のにスムーズさを求めるのであれば、スマホの画面は非常に強いように思えます。
なぜなら、画面が小さい分だけ「写真全体を俯瞰しやすい」からです。
「全体がみえる」ということ
スマホで写真データを補正や加工する場合、「写真全体の状況が把握しやすい」というのは大きなポイントです。
小さな画面の中に写真全体がすっぽりと入りますから、パソコンのモニターなど大きな画面でそれをみるのに比べて、全体の状況はよくわかるのですね。
絵画でいうところの「目から離して見ることで、全体のバランスを確認する(あるいは客観的な目でみる)」ことがしやすいのですね。次回に続きます。