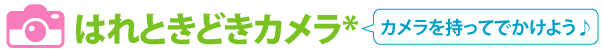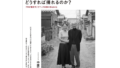前回の記事では「撮り方よりも『考え方』に重点を置いた本」と題して、このタイプの本の選び方についてお届けしました。

今回はその続きです。
本をどう選ぶか
前回の記事では「考え方を書いた本」は、当たりはずれ(自分に合うか合わないか)が大きいことについて書きました。
が、誰だってハズレ本はつかみたくないもの。
では、自分に合った「考え方を書いた本」を選ぶときはどうしたらよいのでしょう。
中身をすべて確認してから判断するのが理想ですが、そうはいかないことが多々あります。そこで今回はネットを使ってできる方法をピックアップしていきます。
技術評論社からでている【「いい写真」はどうすれば撮れるのか?】を例にみていきます。
通販サイトだけでなく出版社のページも確認する
気になる本があるときは、Amazonなどの通販サイトだけでなく、その本の出版社のページも確認するようにしましょう。
より詳しい情報や、通販サイトに掲載されていない情報を確認できる場合があります。
具体例を挙げていきましょう。
たとえば、Amazonでは多くの本が試し読みできますが、中にはできないものがあります。
今回の記事で例に挙げている【「いい写真」はどうすれば撮れるのか?】もそうです。
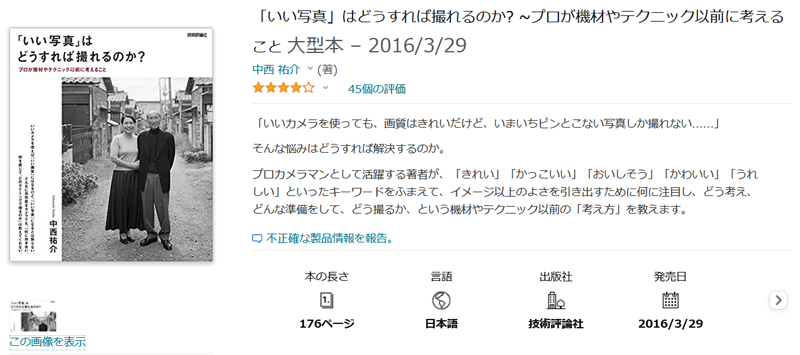
Amazonの商品ページより。確認できるのは表紙のみ。
ためし読みができず、確認できるのは表紙のみ。楽天ブックスも同様です。
……が、出版社のページを見ると、情報の量が段違いです。
なんと
- 目次
- 中身のサンプル
- 著者のコメント
- この本に関連する特集記事
も確認できちゃうんですね。
表紙だけをみたときよりも、本の内容がイメージしやすくなります。
■出版社のページはこちら↓
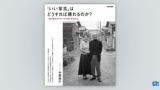
出版社によって情報量は様々ですが、チェックしておいて損はありません。
目次をチェックしよう
本を選ぶ際は、ぜひ目次をチェックしてみましょう。
「考え方を書いた本」の場合は特にですが、目次は各項目の要約になっています。つまり、その本はどんな内容で書かれているのかがわかるんですね。
今回の記事で例に挙げている本も、出版社のページで目次をすべて確認できます。
すると、中身は表紙から受ける印象とずいぶんと違うことがわかります。
この本は特にですが、この目次で「自分に合うか合わないか」がよく分かる本かと思います。
そう、この目次で「その本が対象としている読者層」がみえてくるわけですね。
次回に続きます。