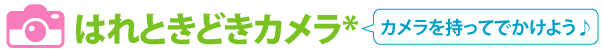前回の記事では「情報整理をする存在」と題して、ネットでの情報収集する際の考え方について書きました。

今回はその続きです。
前回の記事では
前回の記事では、ネットは本と違って、「情報の交通整理がされていないもの」が目の前に出てくるものと書きました。
ネットの情報は
- 情報ごとに作者がおり、それぞれが自分の考えを主張している。
- そのため、方向性がバラバラになるのは当たり前。
- 本とは違い「情報の交通整理をする存在」がいないので、それを行うのは自分自身。
といったところまでお話をしました。
今回はその続きからです。
「区切り(仕切り)がない」ということ
ネットには「情報の交通整理をする存在」がいないということにあわせて、さらに注意しておきたい点があります。
それは
- ネットには、本のように「1冊ごと」という区切りがない
という点です。
いうなれば、「地続き」の状態なんですね。
本との違い
本でしたら、「自分が必要と感じない本、興味のない本」は、なかなか手に取る機会がありません。
つまり、自発的に本を開いて読むという行為をしなければ、その本に書かれた情報は、自分の中に入ってきません。
当然といえば当然のことですが、実はそれが情報選別のフィルターになっていたんですね。
いうなれば、
- 情報が1冊ごとに区切られている
という状態です。
それを自分から開かなければ、そこに書かれた情報は入ってこないわけですね。
向こうから飛び込んでくる
それに対し、ネットの場合は、本のような区切りがありません。
特に今の時代は「自分が求めていない情報も勝手に目に入ってくるしくみ」があちこちでみられるようになっています。
ニュースサイトをみている人、SNSをやっている人であれば、こうした経験は数えきれないほどあるでしょう。
また、ネットの場合は、本のように情報がパッケージされていないので、「情報だけ」がむき出しででてきます。
今のネットは、自分自身が望む望まないは関係なく、そうした情報がむこうから飛び込んでくる状態なのですね。
ですので、本のように「必要ではない本、興味のない本は手に取らない」といった行為をとるのが難しくなっています。
そのため、よほど注意していない限り、「目に入ってしまう」のですね。
つまり、読者は自分が望んだ情報だけでなく、望まない情報もみせられた上で、交通整理をしなければならないわけです。
このように考えてみると、ネットでの情報収集は、決してかんたんなものではないことがわかるかと思います。
次回に続きます。