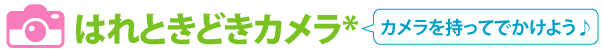前回の記事では「写真のスタイルという概念」と題して、写真の内容や表現方法の是非についてお届けしました。

今回はその続きです。
「自分向けではない」可能性を考える
スマホのカメラに代表されるように、今は誰もがカメラや写真に触れやすい時代になりました。
「機材」という枠にとらわれなければ、多くの人にとって写真を撮るのは特別なことではなく、日常的な行動の1つといっても過言ではない時代になりました。
乱暴な言い方をすれば、カメラが「紙とペン(鉛筆)」のような時代になったのですね。そして、写真は文章のようなもの。
そう、目的や対象によって、紡がれる内容や表現方法が変わるものです。人によって、それが日記だったり、手紙だったり、小説や論文だったりするわけですね。
となれば、答えがみえてきます。
たとえば、中高生が友達に向けて書いた手紙に対して、まったく関係のない他人が
- 文章がなっていない!
- 基本ができていない!
- 人にみせるものじゃない!
などというのは、ヘンですよね。
あるいは、専門的な分野の論文をみて、その分野にまったく興味のない人が
- 面白くない
- 読みづらい
- 意味不明
などというのも、やはりヘンですよね。
なぜなら、それは自分にあてたものではないからです。
「住み分け」という話
ネットが普及して、それまでの時代と変わったことは数えきれないほどあります。
その中で大きなものの1つに「無料でいろいろなものに触れられる」というものがあります。
以前であれば「本や雑誌を買わなければみられなかった」あるいは「買わなければ知ることができなかった」ようなものでも、今は無料でみられたりします。
検索エンジンなどを使えば、今はタダでいろいろなことを見たり、知ることができます。
が、ここに1つの落とし穴があります。それは「垣根の問題」です。
たとえば雑誌

雑誌を例に考えてみましょう。本屋さんに行くと、いろいろな種類の雑誌があります。
それらをみると、雑誌ごとに「対象とする読者」があることがわかります。
いろいろなコーナーをみていくと「明らかに自分は対象じゃないな」という雑誌もあったりします。
そして、買うときは「自分の目的やフィーリングにあったもの」を買います。要は、お金を払っても知りたい・たのしみたいものがそこにあるわけです。
逆に、興味のないジャンルに対して「お金を払ってまで知りたい」と思う人は少ないでしょう。
ネットが今ほど普及する前は、これでおおよその「住み分け」ができていたわけですね。
ところがネットが普及して、タダでいろいろなものに触れられるようになると、それが成り立たなくなります。
特に今は検索エンジンのシステム、情報の共有という概念、SNSの普及などによって、以前のような「垣根」がないような時代になっています。
つまり、本来は「対象としていない人」の目にも入るようになってしまったのですね。次回に続きます。