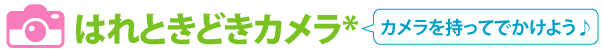前回の記事では「具体的なメニューが思い浮かぶかどうか」と題して、情報にふりまわされる原因、心が揺らいでしまう原因について考えていきました。

今回はその続きです。
前回の記事では
前回の記事では、たくさんの情報に囲まれている中で、「心が揺らぎにくい人」「心が揺らぎやすい人」の例を挙げていきました。
そして、両者の間にある大きな違い――「心の中に具体的なメニューがあるかどうか」について、くわしく解説をしました。
食べ物で言えば、「おいしいもの」を食べたいのは誰でも同じですが、「今日はなんでもいいから、おいしいものを食べたいなあ」と考えていると、目移りしてしまったりして、なかなかメニューが決まらなかったりします。
それに対し、
- 「なんでもいいから、おいしいものを食べたいなあ」ではなく、そこから一歩進んで「今日食べたいのはこれだ!」と具体的なメニューを思い浮かべるようにする
と、目移りをすることなく、メニューをスッと選べるようになります。
情報に関しても同じで、「自分はこういう写真を撮りたいんだ」という具体的なメニューを持っておくと、それが自然と「情報を選ぶ基準」になります。
――といったお話を前回までの記事でお届けしました。今回はその続きです。
自分の目指す方向性をきめておく
物事を学ぶ際には、「自分の目指す方向性」を決めた上で取り組むのが効率的です。
前回の記事でいうところの「具体的なメニューをきめておく」ということですね。
「何でも取り入れる」ができた時代
ひと昔前は、物事を学ぶ際に「いいと思ったことを何でも取り入れる」というスタイルでも有用な部分がありました。
……が、それはあくまで「得られる情報が限られていた時代」のことです。
たとえば、ネットが今ほど普及しておらず、写真の知識を得られる場所が
- 入門書や雑誌などの書籍
- 同じ趣味を持つ仲間との情報交換
ぐらいのものであれば、今と比べればの話ではありますが、個人が得られる情報量はずいぶんと限られていることがわかります。
そうした状況であれば、実際に自分がマスターできるかどうかは別として、「いいと思ったことは全部を吸収しよう」という考え方も十分にありうるでしょう。
なぜなら、知識の総量の目安がみえているからです。
となれば、基本的には
- 書籍あるいは仲間から得た情報を消化していけばよい
わけですね。
また、そもそも情報が出てくるペースも、今の時代と比べればずいぶんとゆっくりです。
ですので、今よりも情報を消化する時間がとれたわけですね。つまり、
- 個人が得られる情報量は限られていた
- 情報を消化する時間が(今よりは)あった
という状況だったため、「何でも吸収しよう」という考え方もアリだったのですね。
実はメリットだったこと
今、「ひと昔前は、得られる情報が限られていた」と聞くと、不便だったんだなあという印象を持つ人もいるかと思います。
が、実は物事を学ぶ際には、かえってそれがメリットになることもあります。
というのも、情報量が限られているときは、基本的に「王道的な写真スタイル」の情報が多くなるのですね。
川でいえば本流ですね。「本流」の情報がメインになり、「支流」の情報はサブ扱いになる。
そのため、目指すスタイル・発信される情報の方向性(あるいは位置づけ)がわかりやすかったのですね。
当時は当時なりに悩みはあったはずですが、今思えば、現在と比べて「何を学んだらいいのか(あるいは、何から学んだらいいのか)」がわかりやすかったように思います。